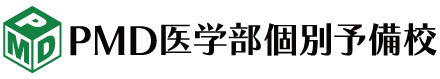共通テスト、英語民間試験の導入見送りについて
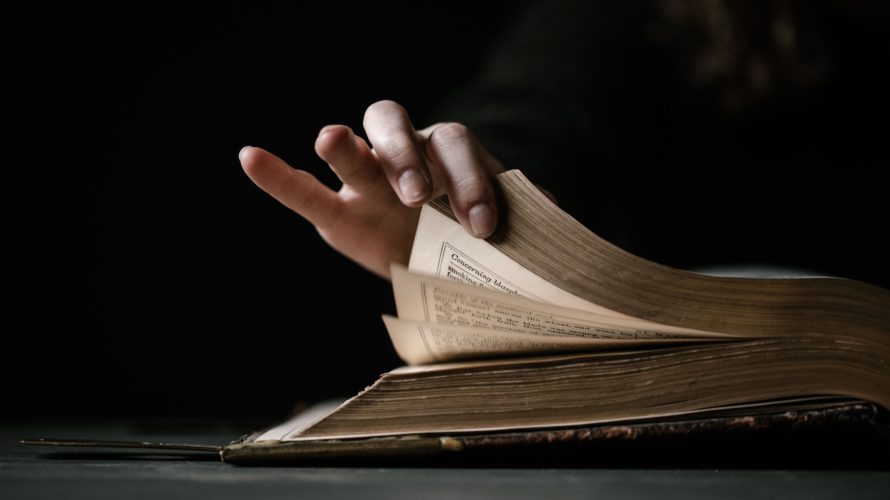

2020年、大学入試センター試験から大学入試共通テストへの移行に伴い、英語試験について民間試験の活用が本格的に始まる予定でした。
しかし2019年11月に萩生田光一文部科学相が民間試験の導入を断念すると発表しました。
なぜ英語の民間試験導入は見送りになったのでしょうか。
萩生田光一文部科学相は延期の理由について、「経済的状況や居住している地域にかかわらず、等しく安心して受けられるようにするためには、更なる時間が必要」とのことでした。
この「経済的状況」について1回あたり5,800円~の受験料が個人負担のため、家庭の事情により受験機会に差が出てしまうことです。
また「居住地域」については、対象となる民間試験のうち47都道府県で受験できる試験は、実用英語技能検定(英検)とGTEC のみで、ケンブリッジ英語検定、TOEFL iBT、TOEIC、TEAP、TEAP CBT、IELTSは受験できる地区が限られています。
英語民間試験一覧
| 検定名 | 実施団体 | 検定料 | 実施地区 |
| ケンブリッジ英語検定 | ケンブリッジ大学 英語検定機構 | 9,720円~25,380円 | 10地区 |
| 実用英語技能検定(英検) | 日本英語検定協会 | 5,800円~16,500円 | 全都道府県 |
| GTEC | ベネッセコーポレーション | 6,700円、9,720円 | 全都道府県 |
| IELTS | ブリティッシュカウンシル、IDP | 25,380円 | 9・10地区 |
| TEAP | 日本英語検定協会 | 15,000円 | 全都道府県 |
| TEAP CBT | 日本英語検定協会 | 15,000円 | 6地区 |
| TOEFL iBT | ETS | 235ドル | 10地区 |
さらに民間試験の実施団体は、新制度導入により2020年度の受験人数などの予想が立たず、試験監督の人数確保や実施に適した会場選びなどの準備に時間がかかり、試験日程や会場の発表が遅れるなど、新制度実施の準備が十分に整っていませんでした。
その他の問題として採点者の人数不足や採点基準が非公表のため採点者によって不公平が生じるといった可能性もあります。

そもそも英語試験について大学入試センター試験から大学入試共通テストはどのように変わり、なぜ民間試験を導入することになったのでしょうか。
近年の国際化に伴い、さまざまな場面で英語を使ったコミュニケーションが必要となってきています。仕事で英語を使う機会も増えていきます。
これまでの大学入試センター試験では読む・聞くの2技能が中心となっています。
(配点は「リーディング」200点、「リスニング」50点)
読む、聞くだけでは不十分であると長年問題視されていましたが、グローバル化が進み、書く(WRITING)、話す(SPEAKING)も含め4技能の力を伸ばすことが重要視され始めました。
その結果共通テストではリーディング、リスニングの配点はともに100点となります。
(ただし、合否判定にあてる配点の比重は、大学の判断で変えられます。)
共通テスト英語の大学毎の配点比もご参照ください。
しかし55万人以上の受験が見込まれるセンター試験(共通テスト)で、書く(WRITING)
、話す(SPEAKING)も採点するとなると膨大な量となるため、すでに書く、話す技能も含めている英語の民間試験を代わりに使う運びとなりました。
しかし冒頭の受験者の不公平さが考慮され、2019年7月に高校側から文科省に導入の先送りの要望が提出され、実施に向けた十分なシステムが構築できていないため今回の民間試験導入の見送りとなりました。
萩生田光一文部科学相は大学入試における新たな英語試験は、新学習指導要領が適用される2024年度入試から導入すると発表し、検討を行っています。
すでに一部の私立大学では英語の民間試験の活用を始めた大学もあります。
受験生が安心して、受験に臨める仕組みになるよう今後の動きに注目していきます。
-
前の記事

2021年度崇城大学薬学部一般選抜(前期) 2020.08.22
-
次の記事

福岡大学医学部、共通テスト利用型(Ⅲ期)について 2020.08.28